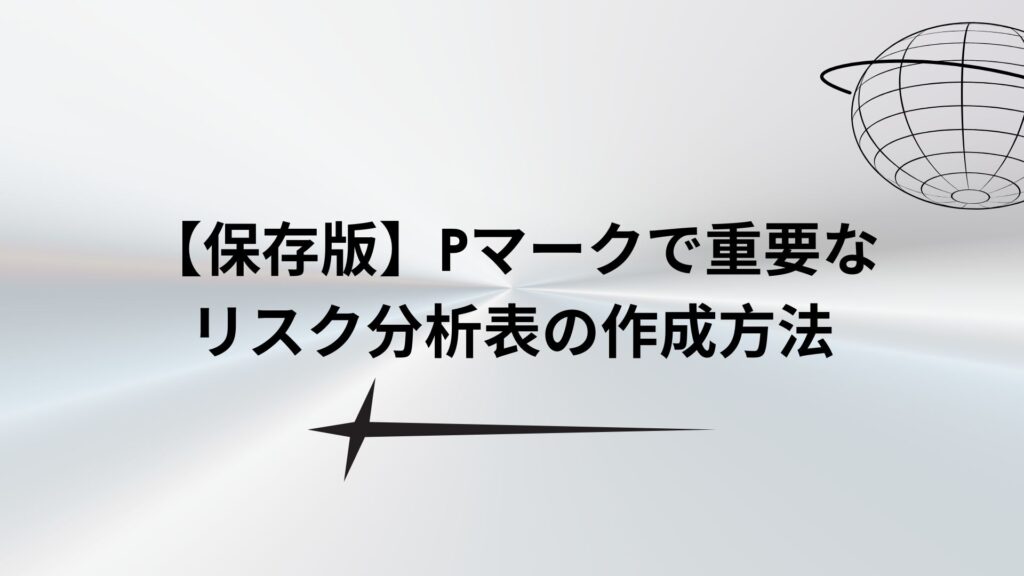
〜個人情報ライフサイクル全体を通じたリスク管理の実践法〜
目次
- Pマークにおけるリスク分析とは
- ISMSとの違いを正しく理解する
- 個人情報のライフサイクルごとに行うリスク把握
- リスク分析表の作り方
- 実務でのリスク分析手順
- 対策整理と記録方法
- 見直しと継続的改善のコツ
- まとめ
1. Pマークにおけるリスク分析とは
プライバシーマーク(Pマーク)を運用するうえで、リスク分析は最も重要なプロセスのひとつです。
JIS Q 15001:2023では、組織が個人情報を取り扱う際に想定されるすべてのリスクを把握し、対策を講じることが求められています。
この分析は、情報資産単位で評価するISMS(ISO27001)とは異なり、
「個人情報の流れ(取得→利用→提供→保管→廃棄)」ごとに発生しうるリスクを全て明確化する点が特徴です。
2. ISMSとの違いを正しく理解する
PマークとISMSでは、リスク分析の目的も手法も異なります。
下記の比較を押さえておくと混同せずに済みます。
| 比較項目 | ISMS(ISO27001) | Pマーク(JIS Q 15001) |
|---|---|---|
| 対象 | 情報資産(データ・設備など) | 個人情報の取扱プロセス |
| 分析の基準 | 機密性・完全性・可用性 | 取得・提供・保管などの業務工程 |
| 手法 | 点数評価・リスク値算出 | 全リスクの網羅的洗い出し |
| 目的 | 情報セキュリティの維持 | 個人情報漏えい防止と管理強化 |
3. 個人情報のライフサイクルごとに行うリスク把握
Pマークのリスク分析は、個人情報のライフサイクル全体を通じて行うのが基本です。
以下の5段階を軸に、それぞれの工程で起こり得るリスクを具体的に洗い出します。
| フェーズ | 内容 | 主なリスク例 |
|---|---|---|
| ① 取得・入力 | 顧客・従業員情報を取得する段階 | 不要な情報収集/誤入力/目的外利用/取得ルールの不徹底 |
| ② 移送・送信 | メール送信やクラウド共有の段階 | 誤送信/暗号化漏れ/誤宛先送信/共有設定ミス |
| ③ 委託・提供 | 外部委託先・業務提携先への提供段階 | 委託契約の不備/再委託リスク/提供記録の未整備 |
| ④ 保管 | 紙や電子データを保管・管理する段階 | 紛失・盗難/アクセス制御不備/持出し管理不十分 |
| ⑤ 廃棄 | 不要となった個人情報を削除・破棄する段階 | 削除忘れ/廃棄手順不明確/紙媒体の残存データ漏えい |
4. リスク分析表の作り方
Pマークにおけるリスク分析表は、「ライフサイクル × リスク × 対策」を一元管理できるように設計します。
下記のようなExcel形式で作成するのが実務的です。
| No | 区分 | 対象情報 | 想定リスク | 発生原因 | 現行の対策 | 改善策 | 管理責任部門 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取得・入力 | 顧客情報 | 不要な情報の取得 | 業務フローの定義不足 | 利用目的の明示 | 年次教育で再確認 | 営業部 |
| 2 | 移送・送信 | 顧客情報 | メール誤送信 | 宛先確認漏れ | 二重確認ルールあり | メール自動BCC導入 | 管理部 |
| 3 | 委託・提供 | 顧客情報 | 委託先の不正利用 | 契約管理の不備 | NDA締結済 | 定期的な委託先評価 | 総務部 |
| 4 | 保管 | 従業員情報 | 紛失・盗難 | 持出管理不徹底 | 鍵付き書庫で保管 | 持出記録台帳を運用 | 管理部 |
| 5 | 廃棄 | 顧客情報 | 削除忘れ | 廃棄手順の未整備 | 廃棄報告書の提出 | 年次監査で確認 | 管理部 |
5. 実務でのリスク分析手順
Step 1:個人情報の流れを可視化する
まず、自社で扱う個人情報が「どのように流れているか」を整理します。
(例:申込受付 → データ入力 → 管理 → 委託処理 → 保管 → 削除)
Step 2:各工程で発生しうるリスクを洗い出す
部署横断的にヒアリングを行い、現場で起こり得るリスクを挙げていきます。
※「まれにしか起こらない」ものもすべて記録対象です。
Step 3:既存の対策を確認
すでに実施しているルール・仕組み・教育などを整理します。
(例:誓約書取得、アクセス権設定、メール送信チェックなど)
Step 4:追加で必要な対策を検討
現行対策で不十分な箇所に対して、改善策を定義します。
(例:「削除手順をマニュアル化」「教育頻度を半年に1回へ」など)
6. 対策整理と記録方法
リスク分析表には、すべてのリスクについて「現行対策」と「追加対策」を明確に書き分けます。
この差分を把握することで、審査時に「改善の仕組みがある」と評価されやすくなります。
| 対策種別 | 具体例 |
|---|---|
| 物理的対策 | 施錠管理、入退室制限、監視カメラ |
| 技術的対策 | アクセス権管理、暗号化、バックアップ |
| 人的対策 | 定期教育、誓約書取得、ヒヤリハット共有 |
| 運用的対策 | 手順書整備、点検記録、チェックリスト化 |
7. 見直しと継続的改善のコツ
リスク分析表は一度作って終わりではなく、継続的に更新することが必須です。
下記のタイミングで見直しを行いましょう。
| 見直し時期 | 主な更新理由 |
|---|---|
| 年1回の定期レビュー | 全体の最新化・審査前対応 |
| 新サービス・業務変更時 | 新しい取扱いプロセス追加 |
| 委託先変更時 | 提供・委託リスクの見直し |
| 事故・ヒヤリハット発生時 | 再発防止策の追加反映 |
更新履歴を残すことで、Pマーク審査時に「改善の証跡」として評価されます。
8. まとめ
Pマークのリスク分析は、個人情報のライフサイクルごとに起こり得るリスクをすべて洗い出し、対策を明確化することが目的です。
点数付けよりも「抜け漏れなく把握し、具体的な行動につなげること」が重視されます。
- ✅ 取得〜廃棄までの流れを整理
- ✅ 各段階でのリスクを網羅的に特定
- ✅ 対策・運用ルールを明文化
- ✅ 年1回以上の見直しで継続的改善
これらを実践することで、実務的かつ審査に強いPマーク運用体制を構築できます。
ISO・Pマークの認証・運用は GCconsulting合同会社にお任せください

GCconsultingは、数多くの企業様のISO・Pマーク取得・運用を支援し、
実態に即したコンサルティングで高い認証率を誇ります。
経験豊富な審査員資格保持コンサルタントが、認証・運用更新にかかる作業時間を約90%削減し、
お客様が本業に専念できる体制づくりをサポートいたします。
💪GCconsultingの3つの強み
① コストパフォーマンスに優れたフルサポート
初期準備から審査当日まで、追加費用なしでフルサポート。
現地審査の立ち会いも標準対応のため、安心してお任せいただけます。
コストを抑えつつ、高品質な支援を受けられるのが当社の特徴です。
② プロ審査員によるコンサルティング支援
GCconsultingでは、ISO審査員資格を持つプロのみが対応。
画一的な支援ではなく、お客様の実態に合わせて柔軟にサポートします。
専任担当が最後まで伴走し、認証対応にかかる社内負担を最小限に抑えます。
③ 情報セキュリティ知識の高さ
単なる認証取得支援にとどまらず、実務レベルのセキュリティ対策までアドバイス。
形式的ではない「実効性のある運用」を重視し、
審査指摘リスクの最小化とスムーズな審査進行を実現します。
「認証を取りたいけれど、何から始めればいいか分からない」――
そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。
合わせて読みたい記事!